#第一章 すばらしき君へ
旅人に手紙を預け、旅人が次に出会うどこかの誰かに渡してもらう。それは宛先のない手紙だけれど、人々はそうやって自分の想いを遠くへ伝えていました。
ポルの手元にある手紙も、そういった種類の手紙でした。
(名前も知らないすばらしき君へ。君がどこにいて何をしているかわからないけれど、そんな私たちが、いつかどこかで出会ったなら、きっとそれはすばらしいことに違いない。私はすばらしい自分になれたなら旅に出ようと思う)
手紙には、そう書いてありました。
すばらしい出会いはどこで起こるのかわかりません。もしかしたら、ポルから向かって行かなくてはならないかもしれませんが、今はまだ慣れしたしんだ時間を仲間たちと過ごしたいと思っていました。
ですが、手紙を出すだけなら。
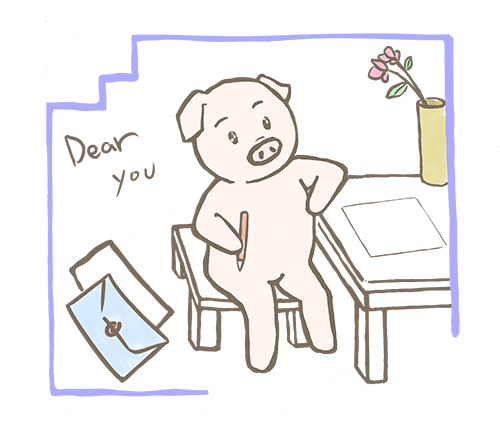
「ねえ、ペンウッドさん。おいらも、手紙を書いてみたいと思うんだ。そして、この前みたいな旅人に頼んで、誰かに渡してもらうんだ」
「そうかい、ポル。いいことだと思うよ。どんな手紙を書くか決めているのかい?」
「それがまだ決められなくて。ずっと考えてみたんだけど、よくわからなくて。フィロとかフワンとかにも相談してみようかな……」
「ポルが書く手紙の内容を、みんなで考えるのはむずかしいと思うな。だって、手紙はポル自身の気持ちを書くものだもの」
「うーん。でも、おいら、何を書けばいいのかわからないんだ」
「それじゃ、みんなにも手紙を書くように勧めてみたらどうだい? そうすれば、みんながどんなことを書くのか参考にできるでしょ。みんなが書いた手紙は、私が預かって、次に旅人が来たときに渡してあげる」
早速、ポルは手紙を書くためのみんなの分の紙と封筒を用意しました。そして、みんなの家を訪問して手紙を書くことを勧めました。すると、みんなはおもしろいと感じたようで、数日後にポルが集めに行くまでに書いておくという約束になりました。
#第二章 みんなの手紙
数日の間も、ポルは手紙に書く内容を一生懸命に考えましたが、結局なにも書けないまま、みんなの家に行くことになりました。
鞄を背負ったポルは、まずフィロの家を訪れました。フィロの家には午後のお茶の時間に合わせて毎日行っていましたが、約束の今日までは手紙の話をしないようにしていました。
フィロは、紅茶とショートケーキをテーブルに並べると、ポルに手紙を渡しました。
「どんなことを書いたの?」
ポルは、イチゴの乗ったおいしいショートケーキを食べながらたずねました。
「私は魔法使いだから、魔法使いらしいことを書いてみたわ」
フィロは封筒を開くと、中の紙をポルに見せました。
(呪文の交換をしませんか。私は、魔法使いのフィロです)
ポルは、紙に書かれた文を何回か読み返してから、フィロにたずねました。
「この手紙を、魔法使いじゃない人がもらったらどうするの?」
「そうね、その人の知り合いに魔法使いがいたら、その魔法使いに渡してくれるかもしれないわね」
「知り合いに、魔法使いがいなかったら?」
聞き返すポルの鼻を、フィロはやさしくなでました。
「ポル、この宛先のない手紙はね、私からの一方的なメッセージなの。だから、難しく考えないで。受け取った人が、どう考えるか、どう行動するかは、その人の自由だと思う」

ポルは黙って紅茶を飲みながら、フィロが言った(一方的なメッセージ)という言葉に感心しました。確かに、そうです。ポルが受け取った手紙だって、誰かが書いた一方的なメッセージです。それを、どう受け取るかはポルの自由でした。
「それとね、ポル。手紙の裏を見てみて」
フィロに言われる通りにポルが手紙を裏返してみると、そこには押し花にした花が貼り付けてありました。ポルには、それがフィロの家の庭に咲いていたスイートピーだとわかりました。
「これ、すごくいいアイデアだね」
「そう? ありがとう」
フィロが喜んでくれたので、ポルはうれしくなりました。そして、自分も相手がうれしくなるような手紙にしようと思いました。ポルは、フィロから手紙を受けとって、大切に鞄にしまいました。
次に訪れたのは、ジータの家でした。
ジータは相変わらず畑にいましたが、ポルに気が付くと、家の中に招いてキュウリをごちそうしてくれました。
「ジータは、どんなことを書いたの?」
「わたしはね、自慢のものを書いたよ」
ジータが封筒から取り出した紙には、
(月ウサギのシチューには、とてもおいしい野菜が入っているよ)
と書いてありました。
ポルはキュウリをかじりながら月のルーのことは書かないのかなと思いましたが、封筒の中に入っているものを見せられて、ジータの自慢は月うさぎにしか採れないシチューのルーより野菜なんだと納得しました。
封筒に入っていたのは野菜の種でした。
「この手紙を、受け取った誰かが、この種を埋めてくれたなら、私の自慢の野菜をその人も食べられるんだよ。いい、アイデアでしょ。まあ、植えたあとは、ちゃんと世話をしないといけないけどね」
「確かに、すごくいいアイデアだと思う」
ポルは、キュウリのお礼を言って手紙を受け取ると、次にバミットの家に向かいました。フワンは、どこにいるのかわからなかったので、最後にします。
バミットの家に行ってベルを鳴らすと、「どうぞ、勝手に入って」と声がしました。ポルが、ドアを開けて中に入ると、バミットは机の上で紙に色を塗っている最中でした。
「ポル、ちょうどいいところに来てくれた。ポルだったら、どの絵がいいと思う?」
机には、封筒と同じ大きさの五枚の紙が並べられていました。
五枚の紙にはそれぞれ違う模様がカラフルに描かれていて、どれも目を引くものばかりでした。ポルは、さすがバミットだと思いましたが、ほめると偉そうにしてきそうな気がしたので、黙って一枚を選びました。
「これかな」
選んだのは、ピンクと青と黄色が淡く混じった模様の封筒でした。
「そうか」
バミットは一人で何回もうなずいては、五枚の絵を見比べ、結局はポルが選んだものとは違う絵を選んで言いました。
「この模様を封筒に描くから、ちょっと待っていてくれ」
「ああ、なるほどね。それ、すごくいいアイデアだね」
ポルは、言ったあとでうっかりほめてしまったことに気が付きましたが、ついでに手紙になんて書いたか聞いてみることにしました。
「オレが、書いたのはこれさ!」
バミットが封筒から取り出した紙には、
(おいしいものをくれた人に、素敵な絵をプレゼント)
と書いてありました。
「な、いいアイデアだろ」
結局、偉そうに自慢されてしまったポルでしたが、ひそかにバミットらしいアイデアだと感心しながら、バミットが封筒に色を塗るのを待つことにしました。
しばらくしてできあがった封筒は、明るい色を組み合わせた模様で、とても楽しげな印象でした。
「じゃ、預かってくね」
ポルは、バミットの家をあとにしてフワンを探すことにしました。
フワンを探しながら、手紙について考えます。誰が読んでもポルらしい気持ちが伝わるような手紙とは、どんな手紙なのか。
フィロとジータとバミットの手紙には、それぞれ自分らしさがありました。それを感じたポルは、改めて自分らしさを考えてみました。
(魔法のビー玉研究家)
確かにポルのことでしたが、おおげさに聞こえるのでやめておきます。
(スキップが上手)
手紙を出してまで伝えたいことではないような気がします。
ポルはため息をつくと、それにしても押し花を入れたり野菜の種を入れたりするアイデアはいいなと、いつの間にか手紙に書く内容よりも、そちらを考えるのに夢中になるのでした。
しばらくしてフワンを見つけたのは、道からはずれたところに生えている木のそばでした。フワンは、葉が全て散った木の枝を見上げていました。
「フワン、こんな所でなにしてるの?」
近づいて声をかけたポルに、フワンは上を見るように言いました。
「ごらんよ。ここから見上げると空の雲が枝に乗っかっているみたいだ。白い綿の木だ」
「ほんとだ……」
しばらく二人してぼんやりと綿の木を眺めましたが、やがて北風が雲を移動させてしまいました。ポルが身震いします。もう、冬なのです。
「ねえ、フワン。手紙書けた?」
「うん、宝箱の中に入っている」
「どんなことを書いたの?」
「そのままのことさ」
フワンは、宝箱から手紙を取り出すとポルに見せました。封筒の中の紙には、フワンらしい言葉が書いてありました。
(宝箱、ただいま空いています。宝物をしまいたい人はお早めに)
ポルは、封筒に紙を戻しました。封筒の中には他に何も入っていませんでした。フワンらしい、素朴な文章と飾り気のないただの封筒です。
「それじゃ、預かっていくね」
そう言ってかばんに封筒をしまいながら、ポルは気づいてしまいました。くすりと笑って、フワンの顔を見ます。フワンはにっこり笑って、ウインクをしました。
封筒の折り曲げて封をする部分に、小さく描かれたものがありました。それは、鍵穴でした。フワンは、封筒を宝箱に見立てたわけです。
「みんな、すごいよ。おいら、どうしよう」
正直な気持ちが、ぽろりとこぼれました。
#第三章 真夜中の誘い
家に戻ったポルは、みんなから預かった手紙をペンウッドに渡しました。そして、それぞれが誰の手紙か説明すると、思い切って相談してみました。
「おいら、みんなみたいな手紙を作れないよ。どうしよう、ペンウッドさん」
「確かに、みんなの個性が良く現れてるよね。文章もそうだし、封筒も工夫してある。ポル、それじゃ、いいことを教えてあげよう。それはね、書けない時は取りあえず書けということさ」
「どういうこと?」
「いきなりすごい文章を書こうとするからアイデアがなかなか浮かばないのさ。まずは自分のこととか日常のこととか、紙にどんどん書いてみてごらん。そうすると、ふとアイデアが浮かんだりするから」
「それなら、おいら、魔法のビー玉のことを書いてみるよ。どんな実験をしたかって、書くの楽しそ!」
「そうか、それは良かった。頑張って」
ポルは、さっそく机に向かって書き始めました。魔法のビー玉の実験を思い出すだけで楽しい気分になり、自然と紙に書く文字が増えていきます。実験の結果はいつも(何も起こらない)なのですが、いろいろな魔法の効果を想像するのは楽しいことでした。
その後、夕食の時間だけ書くのをやめたぐらいで、ポルは夜遅くまで書き続けました。書き込んだ紙の枚数もだいぶ増え、このままでは手紙というよりは日記です。
果たして、すばらしい手紙のアイデアは浮かぶのか。ポルは、また不安になってきました。なんだか、急に部屋の静けさや暗さが感じられ、気持ちを落ち込ませます。
そんな時です。ポルは、大事なことを忘れていることに気が付きました。
「すばらしい手紙のアイデアが浮かぶかどうか、魔法のビー玉で実験すればいいんだ!」
さっそく、ランタンを手にして椅子から立ち上がると、居間へビー玉を入れている小箱を取りに行きました。ペンウッドはもう寝てしまったようで、他の明かりは消えていました。ポルは、壁際の棚から小箱を持ってくると、自室に戻って机の上で開きました。
手のひらにビー玉を乗せると、呪文のように願いを言います。
「魔法のビー玉よ、おいらに、すばらしい手紙の書き方を教えてください。お願いします」
しばらく待っても、何も起こりません。ポルはため息をつきながら、このことも紙に書き加えました。
悩みながらもやもやして机の上にうつぶせると、うっかり机の上の紙を床に落としてしまいました。かがんで紙を拾い机の上に戻そうとしましたが、そこで動きが止まります。
息を潜め、机の上をじっと見つめます。
妖精がいます。小さな体で鉛筆を担いでよろよろしています。ポルと、目が合いました。妖精が気まずそうに笑います。
「や、やあ。何を書いているのかな? こんなに夜遅くまで明かりが見えたので、のぞきに来たんだよ」
ポルはすぐには返事をしないで、じっと妖精を観察しました。今までに何度も妖精にはいたずらされたので、慎重になります。
妖精が、またしゃべりました。
「ねえ、何とか言ってよね。手紙、読んでもいい? きっと、大切な手紙なのね。いいこと、教えてあげましょうか?」
「何も聞きたくない。邪魔しないで」
ポルは妖精から鉛筆を取り上げると、机の上の紙をまとめて机の上に裏返して置きました。
妖精は不満そうな顔をしながらランタンの周りを飛び回ります。妖精の薄い羽がランタンの明かりできらきらと光ります。
「それじゃ、私と遊びましょ」
「遊ばない」
「なんで? 夜なのに起きているときは、こっそりと遊ぶものよ」
「じゃあ、もう寝る」
もう、夜中です。今からまた書き始めても、どうせ妖精が邪魔してくると思ったポルは、手紙のことはまた明日考えることにしました。
ランタンの明かりを消そうと手を伸ばします。すると、妖精が慌てながら言いました。
「すてきな文章が書けないんでしょ?」
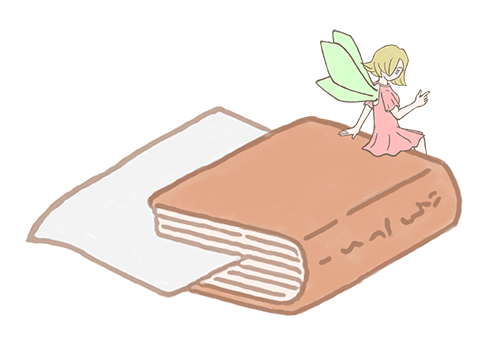
「えっ?」
ポルは、驚いて妖精を見つめました。妖精は、なぜかポルの悩みを知っていました。
「おいらだって、がんばってるんだ。でも、みんなみたいな自分らしい一言が思いつかないんだから。もう、どうしたらいいのさ」
妖精に言うことではないとわかっていましたが、夜遅くまでがんばっても書けない自分に自信がなくなっていたポルは、みじめな気分になりながら、つい不満を言ってしまいました。
言ってから急に恥ずかしくなりました。もう寝てしまった方が良さそうだと思い、再びランタンを消そうとします。
「じゃあ、寝る前におまじないだけしておいたら?」
「おまじない? なんの?」
「すてきな文章を書くおまじないよ」
妖精が教えてくれたおまじないは、簡単なものでした。寝る前に書きかけの紙を本に挟んでおくと、翌朝にすばらしい文章を思いつくというものでした。
それくらいならと、ポルは本棚からペンウッドに借りていた本を持ってきて、本の間に書きかけの紙の束を挟みました。
妖精は嬉しそうに笑いながら、本の周りを何回も飛び回りました。その羽から綺麗な粉のようなものが本に降りかかります。ポルが眠くなってきたまぶたでそれを見ていると、妖精はふっと消えてしまいました。
「おまじないが効くといいけどね」
妖精のおまじないを信じたわけではありませんが、少しだけ不安な気持ちがうすれました。ポルは、ゆっくりと眠りに落ちていきました。
翌朝、目が覚めたポルは妖精とのやりとりが夢だったような気がしましたが、机の上に紙の束が挟まった本が置いてあるのを見て、おまじないのことを思い出しました。
妖精は、素敵な文章が書けるおまじないだと言っていました。ポルは、もしかしてと思いながら机に行って鉛筆を手に取ると、昨夜の続きを書くために本に挟んでおいた紙を抜き取りました。
「なんで!」
悲鳴に近いような甲高い声でポルは叫びました。既に起きていたペンウッドが、慌てて駆けつけます。
「どうしたんだ、ポル。朝から大きな声で」
「だって、だって」
「だから、どうしたの?」
「全部、消えてる!」
なんと、ポルが夜遅くまでがんばって書いた文字が、全ての紙から消えていたのです。
ペンウッドが、それをのぞき込みながら首を傾げます。ポルが白紙を見ながら叫んでいる理由がよくわかりません。
「あ、これ私の本だね。ポルが読んだの?」
そう言いながらペンウッドは何気なく本をパラパラとめくりました。
「なに、これ!」
今度はペンウッドが叫びます。
どのページにも、まるで落書きのように文字が散らばっているのです。ペンウッドは渋い顔をしながらポルに見せました。
「君のいたずらかい」
ポルは、何のことかわからず本を見ました。そして、気が付きました。これは、きっと、妖精のいたずらなのです。
まるで、本が手紙に書かれた文字を吸い取ってしまったようでした。本のあちこちのページにあるのは、確かにポルが書いた文字でした。一文字だったり、単語だったり、文章の切れ端だったりと、もう本の中はめちゃくちゃでした。
せっかく書いた文章が消えて無くなったり、ペンウッドに疑われたりして、とても悲しい気持ちのポルでしたが、皮肉にも手紙に書く言葉が頭に浮かんびました。
(魔法のビー玉研究中。妖精のいたずらには気をつけよう)
まさに今の自分らしいなと、ポルは満足しながら、ペンウッドに妖精のことを、必死に説明するのでした。
#第四章 ビー玉の秘密
雪が降り積もり、いつも見ている景色は白く変わっていました。
「ペンウッドさん。おいら雪かきしてくるよ」
「ああ、頼む。私が作った雪かき棒を試してくれ。あとで、使った感想を聞かせて」
ペンウッドは、暖炉の前でなにやら小さな木材を削りながら言いました。
ポルは、今度はなにを作っているのだろうと気にしながら扉を開けて外に出ました。そして、思わず目をつぶりました。太陽に照らされた真っ白い景色がとても眩しかったのです。
「雪は何で白いのか。ああ寒い、ああ冷たい」
歌うような口振りで独り言を言いながら、外に出たポルは、雪の上に足跡を付けていきました。
ペンウッドが作った雪かき棒は、見た目は長い棒の先に大きめなスコップが付いているだけなのですが、手元にはレバーが付いていました。使うのは初めてですが、ポルは教わったとおりに雪をすくってからレバーを握ってみました。
すると、雪かき棒がしなり、すくった雪を勝手に遠くへ放り投げてくれました。ポルは、全く力を入れていません。ただレバーを握っただけです。
「すごいよ、これ! さすがペンウッドさん」
ペンウッドは自分のことを(作る人)だと言っていました。いろいろなものを作ったり、組み立てたり、なおしたりしています。最近のポルは、そんなペンウッドに憧れていました。
ペンウッドが言っていました。作ることは、ひらめくこと。ひらめくためには学ぶこと。ポルも、毎日がんばっています。
雪かきは順調に進みました。雪の量が多くて大変ではあるのですが、レバーを握って雪を放るのが思いのほか楽しく、あっという間に家の前の雪は減っていきました。
ところが、突然思いがけないことが起こりました。
「うわあ!」
雪かき棒で放った雪が、ポルのそばの大きな木にあたり、枝に積もっていた雪がまとめて落ちてきたのです。ポルは、雪に埋もれてしまいましたが、それでも、がんばってビー玉を取り出しました。魔法のビー玉研究家は、どんな時でも研究を欠かしません。いつ、どんな魔法が起こるかわからないのですから。
「えっ」
ポルは、急に胸の鼓動が大きくなるのを感じました。いつもと、ビー玉の様子が違うのです。
「ビー玉が光ってる!」
ポルが驚いて見つめていると、ビー玉は光りながら宙に浮い上がり、そこに吸い寄せられるように周りの雪が集まっていきました。
雪はどんどん固まっていって、あっというまに雪だるまの形になりました。雪だるまには顔はありませんでしたが、鼻にあたる部分にポルのビー玉が埋まっていました。
「やあ、こんにちは」
雪だるまが、陽気な声で言いました。
突然現れたしゃべる雪だるまにポルが戸惑っていると、家の中からペンウッドが雪かきの様子を見に現れました。
「ポル、そんなところで何をしてるの?」
ペンウッドがポルに近づくと、雪だるまが話しかけました。
「やあ、あなたはペンウッドさんでしたね。ビー玉の姿の時に、お会いしましたね」
しゃべる雪だるまに驚き、目を見開いて見つめたまま、ペンウッドの動きが止まります。
「雪だるまが、しゃべってる……」
「雪だるまではなく、なつかしさの妖精ルルットですよ」
「妖精なの?」
たずねたのは、雪に埋もれたままのポルでした。妖精なら今までも会っているので、そんなに驚くことでもありません。
「正確には、ある年老いた魔法使いが妖精の魔法の力を借りて私を作りました。ほら、その証拠に私の気配を感じて妖精たちがやってきましたよ」
いつの間にか、三人の妖精たちが現れて、ルルットの周りを飛び回ります。
ポルは、小さく「あっ」と言いました。ようやく、わかったのです。何度も妖精に出会うことがあったのは、ビー玉の魔法が原因だったわけです。確かに、毎回ビー玉を取り出した時に妖精は現れていました。
飛び回る妖精たちに囲まれながら、ルルットが話しを続けます。
「その魔法使いは、雪を見ていると何だか寂しい気分になって、昔のことを思い出すことが多かったのです。そこで、私を作って懐かしい気持ちになれる魔法を使わせたのです」
「ふーん」
懐かしさというものがよくわからないポルは、そっけない返事をしながら雪の塊から抜け出すと、地面に落ちている小さな枝やら石やらを拾ってルルットの顔にくっつけました。目と眉毛と口ができました。ついでに、棒もさして腕にします。
「ほら、もっと雪だるまっぽくなった」
「いえ、雪だるまではありません。なつかしさの妖精ルルットです」
正確にはルルットは妖精ではないようですが、ポルは、いつもいたずらされる妖精にお返しができた気がしてうれしく思いました。そんな光景を見て驚いているのはペンウッドでした
「ねえ、ポル。魔法とか妖精のことだったらフィロに相談した方がいいよ」
「大丈夫だよ、ペンウッドさん。妖精なら、おいら何回もあったことあるんだ」
「そ、そうかい。だったら任せるけど」
ペンウッドが少しずつ離れていくのを見ながら、ポルは考えていました。魔法のビー玉のことです。今、ビー玉はルルットの鼻になっています。つまり、ビー玉の魔法でルルットが現れたのか、魔法のビー玉がルルットなのか。考えると、よくわからなくなってきました。
魔法のビー玉研究家として、ポルはルルットに言いました。
「ねえ、おいらのビー玉返して」
「えっ? ビー玉は私でして……。返すというのは、私を渡すということでしょうか。実は、私が魔法を使うには手に乗っけていただく必要がありまして。では、よろしいですか?」
「やだ」
ポルは、さっと手を後ろに隠しました。妖精たちと同じように、いたずらされると思ったのです。
「それでは、ペンウッドさんで」
ルルットはふわっと飛び上がると、ペンウッドの胸元にやってきました。
「さあ、昔のことを思い出して、私を手に乗せてみてください。懐かしい、子供の頃のことでもいいと思いますよ」
ペンウッドはルルットを手に乗せるのをためらいながらも、雪を見てるうちに子供のころのことを思い出していました。無邪気に雪を投げ合っていたような幼い頃です。
「なつかしいな」
そう呟いたときには、自然にルルットを手のひらに乗せていました。
すると、不思議なことが起こりました。降り積もった雪が舞い上がり、固まっていき、やがて二体の子供の姿をした雪像が現れたのです。
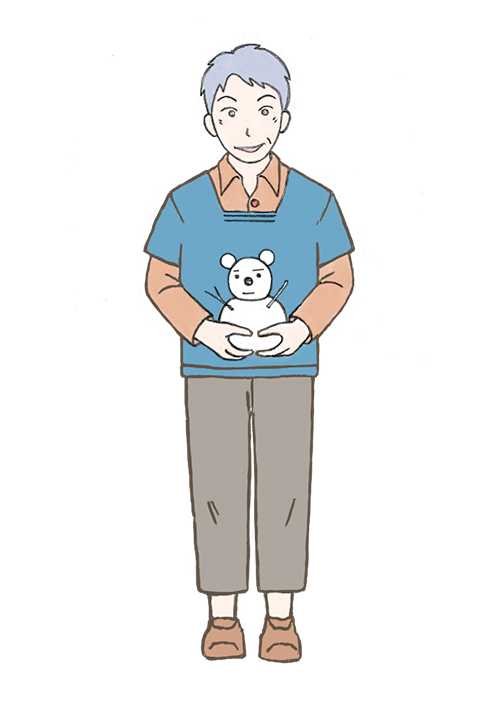
「ああ、みんな……」
ペンウッドは雪像に近づいていきました。そこにあったのは、懐かしい友達の姿でした。
ルルットはペンウッドの手から浮かび上がると、雪の上に降りました。
「私の魔法は、いろいろな人に昔を思い出してもらい、懐かしさを感じてほしいという魔法使いの想いから作られました。春になり雪が溶けて私がビー玉だけになるその時まで、私はあちらこちらに行って皆さんに声をかけることでしょう。それでは、さようなら」
ルルットと名乗った雪だるまは、そのままどこかへ妖精たちと一緒に滑って行ってしまいました。
#第五章 本当の気持ち
レンゲソウの花が咲く野原で、ポルは摘んできた野いちごが入ったカゴを横に置いて、仰向けに寝ころんでいました。
冬が終わり、春になりました。暖かいそよ風が、ポルの鼻を撫でていきます。
魔法のビー玉は、もうポルのところにはありません。ルルットが言っていたように、暖かくなって雪が溶けるのと一緒にルルットも溶け、またどこかにビー玉だけ落ちていることでしょう。
川の中かも知れませんし、どこかの草むらの中かも知れません。
ポルは、鞄からノートを取り出しました。そこには、川でビー玉を拾ってから今までのことが書いてありました。思い返せば、妖精たちや(すばらしい棒)などによって、いろいろな出来事がありました。それは過ぎ去ってはまたやってくる季節とは違い、めぐってくることのない思い出となりました。
ポルは、そのノートのことを(思い出ノート)と呼んでいました。(思い出ノート)を書くようになったのは、ルルットが消えたあの日に(なつかしさ)というものがわからずにいたポルへ、ペンウッドが言った言葉がきっかけでした。
~ポル。君が経験した出来事はやがていつか思い出になる。懐かしさはね、それをふと思い出すきっかけに触れたとき、感じるものなんだよ。それは久しぶりに会う人であったり、引き出しの中から見つけた昔の写真だったり、手紙だったりね。ポル、ノートに思い出を書き記しておくといい。記憶だけではなく、文字にして残しておけば、いつかまたそのページを開いたとき、君はなつかしさを感じるかも知れないよ~
あいにく、今はまだ(思い出ノート)のページをめくっても、懐かしさらしきものは感じません。ただ、日記のように、その出来事を思い出すだけです。
「よく、わかんないや」
ポルは、カゴの中から野いちごをつまむと、また寝ころびました。紫色のレンゲソウの花が咲き広がる野原に、ゆっくりと時間が流れていきます。
うとうとと眠りかけるポルでしたが、ふと誰かの声が聞こえた気がして目を開けました。そして、起きあがってみると、知らない男の人が立っていました。
「やあ、君はこのあたりに住んでいるのかい? ぼくは旅人でね、このあたりをちょうど通りかかったら君の姿が見えたので、声をかけてみたんだ」
「えっ!」
ポルは、驚いて大きな声を出してしまいました。なんと、旅人がやってきました。
「はい、おいらの家はすぐ近くです。みんなの手紙、預かってもらえますか?」
緊張しなら慌ててしゃべるポルの様子を見て、旅人が笑います。
「手紙? ああ、いいよ。旅人はそういうこともしてるからね。でも、私は、こうして旅を途中で出会った人と話をするのが好きなんだ。ねぇ、君のことを聞かせてくれないか?」
そういうと、旅人はポルの横に座りました。
「もちろんです。聞いてくれますか? あっ、これどうぞ。野いちごです」
ポルは、野いちごが入ったカゴを旅人との間に置くと、自分も座りました。そして、ゆっくりと、話し始めました。
それは、ビー玉を拾ってからの出来事であり、ポルの気持ちであり、思い出でした。
いたずら好きな妖精たちとは、ビー玉が無いのでもう会えません。ポルを成長させてくれた(すばらしい棒)も、今はありません。
それでも、ポルはポルらしく思い出を大事にしながら仲間たちと過ごしています。やがて、すばらしい自分になるその時まで。
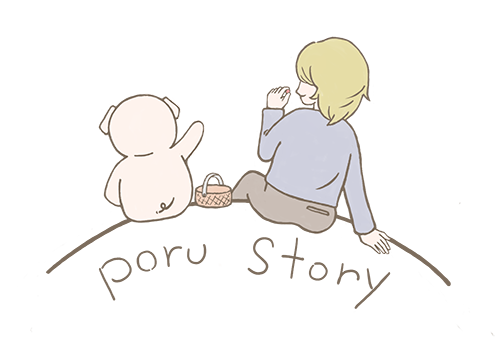
「そうだ」
話し終えたポルは、ふいに手紙を書き直したくなりました。ようやく、何を書けばいいのか本当にわかった気がします。しかも、今すぐに書かなければなりません。なぜなら、手紙で伝えたいのは、物語を伝える喜びを感じた、今の気持ちなのですから。
「旅人さん。少し、待っていてください」
「ああ、いいとも」
ポルは鞄から紙と鉛筆を取り出すと、ノートを下敷きにして今の気持ちを書いてみました。それは、短い文章ではありますが、しっかりとしたポルらしい気持ちでした。
(君に会って話したい)
手紙ができあがりました。
「お待たせしました。それじゃ、おいらの家に来てください。みんなの手紙も渡したいんです。それと、野いちごでケーキを作りますね。おいら、紅茶を淹れるのも上手なんですよ。庭も、見てください。春になって綺麗な花もたくさん咲きましたし、畑に植えた野菜の種も、芽がたくさん出てきたんです」
「伺わせてもらうよ。ありがとう」
その後、旅人を家に招いてもてなしたポルは、ペンウッドからみんなの手紙を受け取って旅人に渡しました。そして、ポルも書き直した手紙を封筒に入れて渡しました。
「なんか、おいらの手紙だけ、何の工夫もないや」
ポルはちょっとだけ残念でしたが、それは諦めることにします。
「それじゃ、野いちご風味な手紙を預かっていくね」
「えっ? 野いちご風味?」
「そうさ、君からもらったのは、甘酸っぱくておいしい野いちごと手紙だからね。だから、私が誰かに君の手紙を届けるときは、野いちごを食べながら聞かせてもらった君の物語を一緒に伝えてあげる。だから、野いちご風味な手紙。君だけの特別な手紙でしょ」
ポルの表情が、パッと明るくなります。
「うん、そうだね!」
いつか誰かに届くに違いないポルの物語。きっとそれは、すばらしい宝物になることでしょう。